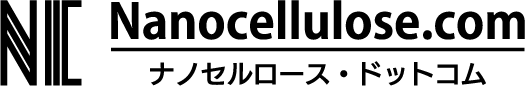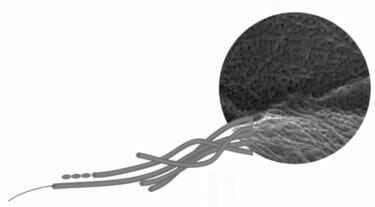ナノセルロース、セルロースナノファイバー(CNF)、セルロースナノクリスタル(CNC)、バクテリアナノセルロース(BNC)に関する、国内・海外の最新ニュースを掲載しています。こちらは 2023 年 2 月に報道されたニュースを、新しいものから順に掲載しています。
- 1 CNFを使って海水で分解するバイオプラ不織布を福井大学などが開発(2023年2月21日)
- 2 ナノセルロース材料国際シンポジウムが発表・参加を受付中(2023年2月21日)
- 3 CNFからAl合金並の強度と自己消火性を兼ね備えた板材を開発(2023年2月18日)
- 4 王子、セルロース繊維で補強した樹脂ペレットを開発(2023年2月15日)
- 5 ドイツの Bioweg、BNC生産で Ginkgo Bioworks と連携(2023年2月14日)
- 6 CNFを使ってミカンにカビの生えない段ボール・不織布を開発(2023年2月14日)
- 7 バクテリアナノセルロースから作られたハンドバックが出品(2023年2月10日)
- 8 スギノマシン、繊維が長く細いタイプのCNFの技術資料を公開(2023年2月7日)
- 9 金沢工業大学とJST、CNFを使用した複合軽量素材の説明会を開催(2023年2月7日)
- 10 昭和丸筒とサンキン、CNFと鋼材の2層パイプを試作(2023年2月4日)
- 11 セルロースミクロフィブリルを使ったルアー(釣り竿)が発売(2023年2月4日)
- 12 東亞合成、中計でセルロースナノファイバー製品を早期に市場投入(2023年2月1日)
CNFを使って海水で分解するバイオプラ不織布を福井大学などが開発(2023年2月21日)
福井大学と東京都産業技術研究センターは、従来からあるバイオポリマーのセルロースナノファイバー(CNF)を練り込みナノ繊維化することで、海水中で分解するバイオマスプラスチック不織布の、新たな製造手法を開発したことを、日本経済新聞電子版が報じました。
こちらの記事は有料会員限定記事のため、詳細は日経新聞のウェブサイトに直接アクセスしたうえで、ご覧ください。
なお、福井大学工学系部門工学領域繊維先端工学講座の藤田聡教授の研究グループでは、海水中で分解する不織布の研究をされており、2022 年に刊行された 福井大学繊維・マテリアル研究センター年報には、海水分解性セルロース複合化ポリエステルナノファイバー不織布という論文が掲載されています。
ナノセルロース材料国際シンポジウムが発表・参加を受付中(2023年2月21日)
The 4th International Symposium on Nanocellulosic Materials (4th ISNCM)が、中国造紙学会の主催で、4 月 21 日から 23 日に北京で開催されます。ウェブサイトが開設され、発表と参加の受付が行われていることが確認されました。
International Symposium on Nanocellulosic Materials(ISNCM:ナノセルロース材料国際シンポジウム)は中国が中心となって開催しているナノセルロースに関する国際シンポジウムで、2017 年の杭州、2019 年の天津、2021 年の広州に続いて、今回が 4 回目です。
現在、発表の申し込みと、参加の申し込みの受付が行われています。詳細は会議のウェブサイトをご覧ください。
CNFからAl合金並の強度と自己消火性を兼ね備えた板材を開発(2023年2月18日)
東京大学と東レリサーチセンターは、木材由来のセルロースナノファイバー(CNF)から、アルミニウム合金並の強度と自己消火性を兼ね備えた透明な板材を開発したことを発表しました。
東京大学大学院農学生命科学研究科のウェブサイト(研究成果)で公表された内容によりますと、東京大学と東レリサーチセンターの研究グループは、木材由来のCNFから、透明で高強度の板状材料を形成することに成功したとのことです。
このCNF板材は、厚みが 1~3 mmで、強度はアルミニウム合金やガラス繊維強化プラスチックなどの軽量構造材と同等です。一方で、これら既存の軽量構造材よりもさらに軽量です。また、この CNF 板材は優れた自己消火性を有し、面方向と厚み方向で異なる熱伝導性を示します。
新規に開発された CNF 板材は、木材由来の透明な構造材料としての活用が期待でき、建築物や輸送機の採光性・視認性の向上に繋がる、新たな構造設計を実現できると考えられます。
詳細は、東京大学大学院農学生命科学研究科のウェブサイトをご覧ください。またこの研究成果は、ACS Sustainable Chemistry & Engineering に掲載されています。
王子、セルロース繊維で補強した樹脂ペレットを開発(2023年2月15日)
王子ホールディングスは、セルロース繊維をポリオレフィン系樹脂の中に均一分散させることで補強した、樹脂ペレットを開発したことを発表しました。
2 月 9 日付の同社のニュースリリースによりますと、開発された樹脂ペレットは、射出成型に使うことができるもので、同社が従来開発したものと同等の曲げ弾性率を持ちながら、高い耐衝撃性(23 kJ / m2)を有していることが特徴です。これによって、従来品では適用困難であった自動車内装材などへの適用が可能になるそうです。
またペレットの着色が抑えられているため、着色ペレットと組み合わせて使うことも可能です。
なお、この樹脂に補強材として用いられているのは、セルロースナノファイバー(CNF)ではなく、セルロース繊維です。
詳細は同社のニュースリリースをご覧ください。
ドイツの Bioweg、BNC生産で Ginkgo Bioworks と連携(2023年2月14日)
ドイツでバクテリアナノセルロース(BNC)から生分解性材料を製造する Bioweg は、アメリカのバイオテクノロジー企業 Ginkgo Bioworks と連携し、マイクロプラスチックを代替するための材料生産を加速することが明らかになりました。
インドの工業メディア Machine Maker のウェブサイトに同日掲載された記事によりますと、2019 年にインド出身の 2 人の創業者によってドイツで設立された Bioweg は、化粧品、パーソナルケア、ホームケア、農業用コーティングなど、さまざまな業界で一般的に使用されているアクリル酸、ポリエチレン、ポリスチレンなどの合成ポリマーを置き換えることができる BNC 製品を開発・製造しています。
Bioweg の製品は、すでにさまざまな企業によってテストおよび実装されており、合成ポリマーの効果的な代替品であることが証明されています。
一方、マサチューセッツ工科大学(MIT)の5人の科学者によって 2008 年に設立されたアメリカのバイオテクノロジー企業である Ginkgo Bioworks は、遺伝子工学を駆使して、産業用アプリケーションとして使うためのバクテリアを生産する企業です。
このほど両社は連携し、マイクロプラスチックの代替品となる生分解性材料を供給することで、マイクロプラスチック問題に取り組むことが明らかになりました。
Ginkgo Bioworksがバクテリアナノセルロース(BNC)の生産を最適化し、Bioweg がさまざまな市場向けに改良された生分解性材料を供給することになります。
Bioweg は、インド政府が進めるマイクロプラスチック汚染の対策プログラムをサポートすることを目指しており、近い将来、マイクロプラスチック代替品の生産施設をインドに設立する可能性があります。
詳細は Machine Makerの記事をご覧ください。
CNFを使ってミカンにカビの生えない段ボール・不織布を開発(2023年2月14日)
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センターは、セルロースナノファイバー(CNF)を使うことで、柑橘類にカビが生えないようにする段ボールと不織布を開発していることが明らかになりました。
毎日新聞社のウェブサイトの地域ニュース~愛媛~に 2 月 13 日に掲載された記事によりますと、紙産業技術センターでは、温州ミカンなど柑橘の輸送時に使う段ボールや、個別包装用の不織布に抗菌剤を塗ることで、抗菌・抗カビ効果を高める技術を生み出しました。
段ボールなどに抗菌剤を塗ろうとすると、塗り終えるまでに液体内で抗菌剤が沈降し、安定して付着させることができませんでした。そこで抗菌剤に CNF を混ぜることで、抗菌剤の沈降を防ぐことができ、段ボールや不織布に抗菌剤を均一に付着させることができたそうです。
抗菌剤、塗工用接着剤と CNF で構成する液体を用意し、CNF の割合を変えて実験したところ、CNF を重量比で7.7~8.3 %加えて段ボールに塗ると、粒子状の抗菌剤が均一に付着することが電子顕微鏡で確認できたとのことです。さらにカミ商事と共同で、段ボールの製造過程で抗菌剤を塗った製品を試作したところ、CNF を使わない場合は塗る作業が始まって 15 分ほどで抗菌剤の付着量は 3 割ほど落ちましたが、CNF を使った場合は時間が経過しても抗菌剤付着量は変化しませんでした。
なお抗菌剤は、米食品医薬品局(FDA)が認可した、銀イオンの抗菌作用による製品を使ったそうです。
詳しい内容は毎日新聞のウェブサイトからご覧ください。
バクテリアナノセルロースから作られたハンドバックが出品(2023年2月10日)
フィンランドのデザイナー、マリ・コッパネンは、バクテリアナノセルロース(BNC)から作られた 100 %生分解性のハンドバッグ Ferna (2022) を、ストックホルムで開催中の展示会に出品しています。
ウェブメディア E-magagine by ArchiExpo に 2 月 8 日に掲載された内容によりますと、ストックホルムデザインウィークと同期して開催されているストックホルム家具見本市(2 月 7~11 日)に、バクテリアナノセルロース(BNC)から作られたハンドバック Ferna (2022) が出品されています。これはフィンランドのデザイナー、マリ・コッパネンが制作したもので、茶色の色は、細菌の色に由来するものです。
このハンドバッグは長持ちするように作られていません。そして分解することができます。乳酸菌と各種酵母の共生発酵の過程で、Ferna の原料となる素材である BNC が出来上がります。Ferna を糖類、紅茶、酢酸の混合物に入れることで、プロセスを再開し、バッグを複製することが可能です。
バックの写真と詳しい内容はもとの記事をご覧ください。
ナノセルロース・ドットコム コメント
このバクテリアナノセルロース(BNC)は、酢酸菌だけを使って製造されたものではなく、酢酸菌、酢酸菌、酵母など、複数の細菌の共生培養(SCOBY)で作られたもののようです。
酢酸菌だけから作られた BNC は白色をしており、ナタデココとして食用にもされます。
一方、SCOBY で作られた BNC は茶色をしており、コンブチャ(かつては、紅茶キノコと呼ばれていました)を作ったときに、水面にできる寒天状の物質のことです。
スギノマシン、繊維が長く細いタイプのCNFの技術資料を公開(2023年2月7日)
スギノマシンは、独自の独自のウォータージェット製法で製造したセルロースナノファイバー(CNF)の技術資料を公開していますが、従来のものよりも繊維長が長く繊維径が細い BiNFi-s RMa タイプに関する基礎物性や、従来の CNF との違いなどの技術資料を公開したことを、ニュースリリースで発表しました。
本日付けの同社のニュースリリースによると、繊維長の異なるさまざまな CNF を提供していく中で、市場からの要望が大きかった、より繊維長が長く繊維径が細い CNF として、BiNFi-s RMa タイプを新たに追加し、ラインアップを拡充しました。この RMa タイプについて、既存の IMa(極長繊維)タイプとの違いや基礎物性等、役立つ情報をまとめた技術資料(テクニカルレポート)を公開したとのことです。
RMaタイプの特徴は次の通りです。
- 平均繊維径は 9.6 nm(SPM観測による)
- 機械解繊 CNF の中では最も細いナノファイバー
- SPM の視野角である 5 µm を超える長さの繊維が多く観察される
- 解繊不足繊維の残存数が極めて少ない
- フィルムに成形したときの弾性率は、従来の長繊維タイプの約 1.8 倍
テクニカルレポートは同社の Webサイト からダウンロードできますが、会社名、部署名、氏名、住所、電話番号の記入が必須となります。
詳細は同社のニュースリリースをご覧ください。
ナノセルロース・ドットコム コメント
一般的にウォータージェット法による CNF の製造は、薬剤を使用しませんが、他の方法に比べて多くのエネルギーを消費するといわれています。また処理の際に、固形分濃度を低くする必要があります。また一般論として、ウォータージェット法による処理回数を増やせば、繊維径を細くすることが可能ですが、エネルギー消費量も価格も上がるはずです。
環境配慮型の材料としてCNFをアピールするのであれば、製造に要するエネルギー量を明らかにすべきですし、何より、この方法で製造したCNFの水溶液の固形分濃度がいくらで、乾燥重量あたりの価格がいくらなのでしょうか。基礎物性よりも、そちらの方が重要だと思います。
金沢工業大学とJST、CNFを使用した複合軽量素材の説明会を開催(2023年2月7日)
金沢工業大学と国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)では、金沢工業大学が開発した、セルロースマイクロファイバー(CMF)やセルロースナノファイバー(CNF)などの繊維を他の材料と複合化することによって、軽量で高強度の材料を用い積層成形するという技術を、2 月 28 日にオンライン開催する新技術説明会で発表することを公表しました。
科学技術振興機構(JST)は大学等が公的資金を使って実施した研究成果(特許)の実用化(技術移転)を目的に、新技術や産学連携に関心のある企業関係者に向けて、研究者(=発明者)自らが直接プレゼンする、新技術説明会を開催しています。
2 月 28 日に金沢工業大学が実施した 4 つの研究成果の発表が行われますが、その中にCMF や CNF などのバイオマス繊維を強化材に用いた積層複合軽量素材についてのプレゼンが行われます。研究者は、金沢工業大学 バイオ・化学部 応用バイオ学科の附木貴行講師です。
高強度、高弾性、低熱膨張のナノ/マイクロセルロース繊維は、低荷重、低負荷が要求される二輪自動車用ヘルメットや競技用ヘルメットの積層部材への利用が考えられており、軽量性や力学物性の向上がより一層求められているそうです。
今回の新技術の特徴としては、
- 微細構造を有するナノ/マイクロセルロース繊維のハイブリット積層体を成形
- 樹脂含侵性による成形加工が可能な積層体
- 軽くて強い積層複合材
想定される用途としては、
- スポーツ用品
- 家電家具
- 輸送機
とのことです。
詳細は、新技術説明会のウェブサイトをご覧ください。
昭和丸筒とサンキン、CNFと鋼材の2層パイプを試作(2023年2月4日)
紙・樹脂の巻き芯の製造・販売を手掛ける昭和丸筒、昭和プロダクツと、鋼管メーカーのサンキンは、セルロースのファイバー(CNF)と鋼材から成る 2 層パイプの試作品を開発しました。
2 月 3 日付の日刊産業新聞電子版に掲載された記事によりますと、両社は脱炭素に貢献する素材として注目を集める CNF と鋼材を組み合わせることで、パイプの軽量化と高強度化の同時実現を目指すそうです。
日刊産業新聞の記事はこちらからご覧ください。
セルロースミクロフィブリルを使ったルアー(釣り竿)が発売(2023年2月4日)
ルアーメーカーのメガバス(浜松市)は、セルロースミクロフィブリルを骨格とす素材を釣り竿のブランクス(竿の部分)に使ったルアー(釣り竿)を発売したことが明らかになりました。
釣りの総合ニュースサイトであるルアーニュースRに 2 月 3 日に掲載された記事によりますと、ルアーメーカーのメガバスから発売されたルアー OROCHI X10 には、自然素材から採取されるセルロースミクロフィブリルを骨格とする植物系天然繊維を主軸として構成したオーガニックファイバーブランクスが採用されているそうです。
X10 オーガニックファイバーブランクスの特徴は次の通りです。
- ファイバーグラス素材を上回る引張強度を実現した
- 軽量化されており、比重はカーボンファイバーよりも軽い
- 制振性能と衝撃吸収性能が向上。
- 製造過程におけるCO2排出量をカーボンファイバーロッドの20分の1にまで低減
詳しい内容はルアーニュースRの記事をご覧ください。
記事によると、釣り竿の竿の原材料として使われているのはセルロースミクロフィブリルとのことです。一般的にセルロースミクロフィブリルは、セルロースナノファイバー(CNF)より繊維の平均径が大きい繊維を指しますので、今回使われたものは、繊維の平均径が100nmを超えるセルロース繊維と推定されます。ただセルロースミクロフィブリルは、CNFの最小単位という意味としても使われる場合もあります。詳しくは下の記事をご覧ください。
ナノセルロースとは ナノセルロースは、ナノサイズ(縦、横、高さのいずれかが1~100nm(ナノメートル、1nm = 1/1,000,000 mm))のセルロースのことです。 まずセルロースは、グルコース(ブドウ糖)が結合したポリマーで、[…]
東亞合成、中計でセルロースナノファイバー製品を早期に市場投入(2023年2月1日)
東亞合成グループは、中期経営計画 Leap Forward to the Next 2025 において、伸ばす事業に経営資源を積極投入し、国内外での展開を加速するという重要施策を打ち出しましたが、その対象事業として、セルロースナノファイバー製品が明記されています。
1 月 31 日に公表した中期経営計画 Leap Forward to the Next 2025 は、2023 年から 2025 年の3年間を対象とするものです。
- 新製品・新技術の開発力強化
- 海外売上高の拡大
- 持続可能な社会の実現に貢献、
の 3 つを基本方針とし、これを実現するための重要施策として、
- 伸ばす事業に経営資源を積極投入し国内外での展開を加速
- 研究開発力の強化
- デジタルトランスフォーメーション(DX)推進を浸透・拡大、
を進めていくそうです。
この中で、伸ばす事業の具体例として、将来を担うセルロースナノファイバー製品、メディカルケア製品が挙げられており、早期に市場投入し実績化を図るとのことです。
詳しくは東亞合成のニュースリリースをご覧ください。