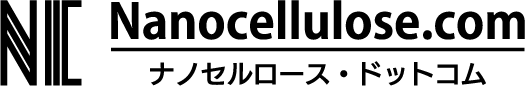ナノセルロース、セルロースナノファイバー(CNF)、セルロースナノクリスタル(CNC)、バクテリアナノセルロース(BNC)に関する、国内・海外の最新ニュースを掲載しています。こちらは 2023 年 1 月に報道されたニュースを、新しいものから順に掲載しています。
- 1 スギノマシン、利昌工業、大建工業がCNFを使ったフローリング材(2023年1月31日)
- 2 西光エンジニアリング、低価格化したCNF濃縮品を販売へ(2023年1月28日)
- 3 パナソニック、セルロースファイバー成形材料の量産販売開始(2023年1月27日)
- 4 日建ハウジングシステム、竹CNFを使った遮熱塗料を開発(2023年1月18日)
- 5 ワシントン州立大学、CNCで果樹を冷害から守る研究(2023年1月17日)
- 6 ペンシルベニア州立大学、CNCの乾燥と再分散メカニズムを解明(2023年1月12日)
- 7 東北大学、CNFシート材に半導体特性を発見(2023年1月11日)
- 8 eiicon companyがCNFオープンイノベーション共創パートナーを募集(2023年1月10日)
- 9 静岡産業大学、CNFを活用した商品開発に従事(2023年1月4日)
- 10 米豪の大学、ナノセルロースを使った農業用肥料を開発へ(2023年1月4日)
スギノマシン、利昌工業、大建工業がCNFを使ったフローリング材(2023年1月31日)
スギノマシン、利昌工業、大建工業は、NEDOの助成事業の一環として、セルロースナノファイバー(CNF)を使った複合フローリングを試作し、スギノマシン労働組合の新事務所に実装したことを発表しました。
スギノマシンが本日、ニュースリリースで発表した内容によりますと、この複合フローリングはスギノマシンが製造した CNF(商品名:BiNFi-s®)を利昌工業が板状に成形し、大建工業が積層して複合フローリングに加工したものです。植物由来材料を主成分としながら高い硬度を保持している点が特徴です。CNF を使用した複合フローリングの実装例としては、日本初となります。
スギノマシンは CNF を高品質・低コスト・低 CO2 排出量で製造する技術を開発しています。一方、利昌工業と大建工業では、CNF を板材に成形加工し、樹脂を含浸させることで耐水・耐湿性を向上させ、床材として適用可能な高機能板材を開発しています。3 社は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業「炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発」に採択されたそれぞれの開発テーマに取り組んでおり、テーマの成果を融合することで実用化の方向性を見いだしました。
樹脂を含浸させた CNF 製板材は、CNF の優れた力学物性を活かし、高強度・高弾性(高硬度)を実現しています。その樹脂を含浸させた CNF 製板材から製造した複合フローリングは、硬度が高いため、木材由来でありながら靴やキャスターによる傷や跡がつきにくく、鉱物製(大理石など)床材の代替として期待されています。
なお詳しい内容は、スギノマシンのニュースリリースをご覧ください。
西光エンジニアリング、低価格化したCNF濃縮品を販売へ(2023年1月28日)
西光エンジニアリングは、セルロースナノファイバー(CNF)の濃縮品の生産・販売を 2 月より行います。これはマイクロ波を使って、従来の CNF 溶液と比べて 10 倍程度、固形分濃度を高めたものです。
あなたの静岡新聞に本日掲載された記事によりますと、静岡県藤枝市の乾燥機メーカー・西光エンジニアリングは、隣接する食品加工子会社の沖友の敷地内に設置した、マイクロ波減圧乾燥機を使って、一般的な CNF 溶液よりも水分量の少ない CNF 溶液の生産・販売を行います。これはマイクロ波で水分子に振動を起こして蒸発させる、電子レンジと同様の原理によるものです。
一般的な CNF 溶液の固形分濃度が 2 %(水分濃度が 98 %)なのに対して、同社が生産する CNF 溶液の固形分濃度は 20 % 程度になります。
また記事によると、CNF は加熱すると変質しやすいため、通常は水に混ぜた溶液の状態で取引され、輸送費がかさむ上、CNF を取り出すのに高額な特殊薬剤で脱水処理が必要となるなど課題が多いそうです。西光エンジニアリングは、使い勝手の向上や流通コスト削減に貢献するため、茶やドライフルーツなどの製造で培った乾燥技術を応用して、濃縮化に成功したとのことです。
詳しくはあなたの静岡新聞の記事をご覧ください。
ナノセルロース・ドットコム コメント
CNF 溶液を濃縮する際の課題は、濃縮によって CNF の繊維同士がくっついてしまって、分散性が損なわれることです。CNF は繊維径が細いことが、その特性を発揮する理由の一つですが、繊維同士がくっついてしまうと、ただのセルロース繊維になってしまいます。なお、海外での工業化事例を含め、ナノセルロース溶液の濃縮は減圧蒸留やスプレードライヤーによって行われるのが一般的なようです。
パナソニック、セルロースファイバー成形材料の量産販売開始(2023年1月27日)
パナソニックプロダクションエンジニアリング株式会社は、植物由来のセルロースファイバーを 55 % の濃度でポリプロピレンに配合した成形材料 kinari の量産販売と通販サイトでの試料用材料の販売を開始したことを発表しました。
この素材は、セルロースナノファイバー(CNF、繊維の半数以上の径が 100 nm 以下)よりも径が太い、セルロースファイバーが使われています。もともとは環境省の CNF 関連の補助事業で、家電製品の筐体への適用を目指してパナソニックが開発したものです。
製品名は、kinari CeF55-PP で、仕様は次の通りです。
- 組成:セルロースファイバー 55 %、ポリプロピレン他 45 %
- 弾性率:3.80 GPa
- 密度(g/立方センチメートル):1.15 g / m3
- ペレット色:乳白色
パナソニックグループでは、この素材の特長と優位性を活かし、車載機構・内装部材、ハウジング内装部材、大物家電外装、美容家電、服飾衣料品、日用品、飲料・食品容器等への展開も進めていくそうです。
詳しい内容は PR TIMES のニュースリリースをご覧ください。
日建ハウジングシステム、竹CNFを使った遮熱塗料を開発(2023年1月18日)
放置竹林問題解消に向けて、竹の活用を加速するため、日建ハウジングシステムなどは、竹から作ったセルロースナノファイバー(CNF)を混ぜた、遮熱塗料を開発したことが、本日明らかになりました。
ハウジング・トリビューン Vol. 654(2023 年 1 号)に掲載された内容によりますと、塗料を開発したのは、日建ハウジングシステムとアマケンテック(熊本県天草市)です。
日建ハウジングシステムは 2017 年度に、環境省の「セルロースナノファイバー活用製品の事業委託業務」に採択され、アマケンテック、中越パルプ工業、熊本大学、鹿児島県薩摩川内市などと一緒に、竹 CNF を使用した建材の開発などを行っていました。この事業の終了後も日建ハウジングシステムとアマケンテックは共同開発を進め、遮熱塗料「ナノ・クールA CNF」を開発したとのとです。
2022 年 11 月には鹿児島県薩摩川内市の複合商業施設「SOKO KAKAKA」に「ナノ・クール A CNF」を塗装して調べたところ、塗装していない場合と比較して室内温度を 4 ℃下げられることが確かめられました。
遮熱塗料の販売価格は 10,000円 / kg で、今後は全国展開するとのことです。
なお CNF の原料となる竹は薩摩川内市市内で伐採されたものを使い、中越パルプ工業 が CNF に加工しているとのことです。
詳細はハウジング・トリビューンの記事をご覧ください。
もとの記事に、遮熱塗料のメカニズムとして CNF に断熱性があることが理由と書かれていますが、 CNF には断熱性はありません(→ 下の記事「ナノセルロースの特性」をご覧ください)。中越パルプ工業が採用している方法で作った CNF は、単一の CNF まで解繊されていないため、木材やパルプと同様、熱が伝わりにくい性質があるものと推測されます。次に、塗料の遮熱性能について、11 月に行った実証実験で、室内温度を 4 ℃下げたと記載されていますが、遮熱塗料は真夏の日射による室内温度の上昇を防ぐのが目的で使われるものなので、7~8 月の外気温が 30 ℃を超えるときにテストするのが一般的です。11 月にテストすることに、どのような意味があるのか、極めて疑問です。
なお遮熱性能の評価については決まった方法がなく、やり方によってはどんなデータでも得られるので、建築関係者、塗装業者の間でさえ、遮熱塗料の有効性については、意見が分かれています。
セルロースナノファイバー、セルロースナノクリスタル、バクテリアナノセルロースなどのナノセルロースには、さまざまな優れた特性があります。 ただナノセルロースの可能性を強調したいがために、特性を誇張しすぎているようにも思います。ここでは、[…]
ワシントン州立大学、CNCで果樹を冷害から守る研究(2023年1月17日)
セルロース ナノクリスタル (CNC) などの植物由来のセルロースベースのナノ物質を含む水溶液を植物に散布すると、断熱層ができ、低温に対する耐性が向上することがわかりました。この水溶液は既存のスプレー装置で塗布でき、1 回の処理で効果が持続します。
農業関係のウェブサイト Growing Produce に 1 月 16 日に掲載された記事によりますと、米国・ワシントン州立大学の Matthew Whiting 教授は、CNC などから成る水溶液をスイートチェリー、リンゴ、ブドウなどに散布しコーティングすると、未処理の場合に比べて芽が環境中に放熱する速度が遅くなり、低温に対する耐性が向上することを実証しました。しかも既存のスプレーで塗布でき、1 回の処理で効果が持続します。
休眠中のチェリーを使った 2020 年の試験では、1 % または 3 % の CNC を含む溶液の処理によって、24 時間後に耐性が最大 6°F(= 3.3 ℃)、72 時間後にはより高い濃度の CNC が効果的であり、耐性が 8.7°F(=4.8 ℃)向上しました。効果は、散布後 24 時間以内に現れます。
一方、チェリーのつぼみを使った研究では、フィールドで散布後 72 時間で、2 % CNCを散布した場合、 23°F (=−5 ℃)で損傷はゼロでしたが、散布しなかった場合は 50 %が損傷を受けました。
国連食糧農業機関(FAO)によると、寒冷による被害は、温帯の果樹への悪影響として世界第 1 位だそうです。
現在、Matthew Whiting 教授らは知的財産を確保したうえで、適用する農家を募集しているとのことです。
詳細は、Growing Produceの記事をご覧ください。
ペンシルベニア州立大学、CNCの乾燥と再分散メカニズムを解明(2023年1月12日)
ペンシルベニア州立大学の化学工学研究者のチームは、セルロースナノクリスタル(CNC)の乾燥メカニズムについての研究で、もとの CNC の機能性を完全に維持しながら、乾燥した CNC を水性媒体に再分散させることに成功しました。この結果は、CNC の保管と輸送が容易であることを示すものです。
ペンシルベニア州立大学(PennState)のウェブサイトのニュースに 1 月 11 日に掲載された記事によりますと、CNC は髪の毛のような形状の末端に負に帯電したセルロース鎖を持っています。水に再分散させると、電気立体反発の結果として、毛髪状の部分は互いに反発して分離し、液体を介して再び分散します。
毛髪状粒子が再分散された後、研究者らはそれらのサイズと表面特性を測定し、それらの特性と性能が一度も、乾燥されたことのない CNC と同じであることを発見しました。彼らはまた、粒子が良好に機能し、さまざまな塩分濃度と pH レベルのさまざまな液体混合物で安定性を維持できることも確認しました。
CNC は、高塩濃度でも再分散することができます。過酷な媒体でも機能を維持し、幅広い用途で使用できる可能性があります。この特性は、添加剤やエネルギー集約的な方法を使用せずに、ナノセルロースの持続可能で大規模な処理への道を開く可能性があります。
この研究成果は、1 月 17 日公開の Biomacromolecules に掲載されます。
詳しくは PennState のニュースをご覧ください。
東北大学、CNFシート材に半導体特性を発見(2023年1月11日)
東北大学は、セルロースナノファイバー(CNF)の組織を制御したナノサイズのシート材に、半導体特性が発現することを見出したと発表しました。高純度シリコン(Si)素材やレアメタルを用いた化合物半導体に代わる、安価で無害のバイオ素材による半導体を作ることができる可能性があります。
東北大学が 1 月 10 日にプレスリリースで発表した内容によりますと、東北大学未来科学技術共同研究センターの福原幹夫リサーチフェロー、同大学大学院工学研究科附属先端材料強度科学研究センターの橋田俊之教授らの研究グループは共同で、CNF 組織を制御したナノサイズのアモルファスケナフセルロースナノファイバーシートに、半導体特性が発現したことを確認しました。
ケナフはアオイ科の植物で、木材パルプの代わりに、製紙原料としても用いられているものです。
半導体特性とは、具体的に、CNF 組織を制御したナノサイズのシート材の I(電流)-V(電圧)特性は、負電圧領域に顕著な現象を示すn型半導体特性を示しました。また直流通電時の並列回路(低伝導帯)から交流通電時の並列回路(高伝導帯)に変化する特性も示しました。
このような特徴から、高価な高純度シリコン(Si)素材やレアメタルを用いた化合物半導体と異なり、低廉で無害のバイオ素材による半導体作製の可能性も出てきました。また日本に豊富に存在する森林資源を活用することで、植物由来の半導体によるペーパーエレクトロニクスの実用化が期待されます。
詳細は大学のプレスリリースをご覧ください。
eiicon companyがCNFオープンイノベーション共創パートナーを募集(2023年1月10日)
オープンイノベーションプラットフォームAUBA(アウバ)を運営するeiicon companyは、富士市より受託した「デジタルツールを活用した CNF オープンイノベーション促進事業」の一環として、本日より、「富士市 CNF プラットフォーム」の普及啓発と用途開発等を目的に、同会員企業 5 社の共創パートナーの募集を AUBA で開始したことを発表しました。
富士市では 2019 年 11 月に富士市 CNFプラットフォームを設立し、CNF(セルロースナノファイバー)の実用化に向けた支援や、用途開発の加速、関連産業の創出・集積を図るための産学金官等の連携・ネットワーク構築などを進めており、2022 年 12 月 21 日の時点で、会員数は 186 です。
富士市では、CNF のさらなる実用化及び用途開発を進めるために、さまざまなプレーヤーを巻き込み、オープンイノベーションによるCNFの利活用に関する議論やアイディア出し、活用方法や技術のすりあわせなどを行う場が必要と考え、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム AUBA を運営する eiicon company に対し、「デジタルツールを活用した CNF オープンイノベーション促進事業」を委託しました。
そしてその委託事業の一環として、相川鉄工株式会社、大昭和紙工産業株式会社、東洋レヂン株式会社、日本製紙株式会社 研究開発本部、ユニチカ株式会社のパートナー企業の募集を、オープンイノベーションプラットフォーム AUBA で本日から開始ました。
今後は eiicon company の支援によって、レクチャー、コンサルティングなどを行いながら、年度内のマッチング、さらにオープンイノベーションによるCNFの実用化・社会実装を行うそうです。
詳細は eiicon company のプレスリリースをご覧ください。
静岡産業大学、CNFを活用した商品開発に従事(2023年1月4日)
静岡産業大学経営学部 3 年生 16 人が、静岡県内企業 2 社が進めるセルロースナノファイバー(CNF)を活用した商品開発に携わっているという記事が、あなたの静岡新聞(静岡新聞のウェブ版)に本日掲載されました。
記事によりますと、学生と一緒に CNF を活用した商品開発を行っているのは、大昭和加工紙業(富士市)とアッパーズ(清水町)の2社で、大昭和加工紙業が CNF を添加した接着剤を用いて製品化した板紙「ICBボード」を使って、アッパーズがあんどん(照明器具)を開発しており、ICB ボード製サイドパネルのデザインの考案を学生に依頼したという内容です。訪日旅行者が喜ぶ、茶畑越しの富士山や駿河湾の深海魚などのデザインを検討しているとのことです。
詳しくはあなたの静岡新聞の記事をご覧ください。
学生が担当しているのはあんどんのデザインで、CNF とは直接関係ありません。また CNF を使った板紙をあんどん(照明器具)に使うという用途も、必ずしも CNF の特性を活かした使い方ではありません。記事には CNF が環境に優しい素材とも書かれていますが、これも意味がよくわかりません。静岡新聞はとにかく CNF の話題を発掘したいようですが、いろいろな意味で無理があるように思います。
米豪の大学、ナノセルロースを使った農業用肥料を開発へ(2023年1月4日)
ニューヨーク州立大学ストーニー・ブルック校と、オーストラリアのクイーンズランド大学では、57 万ドルの研究資金を得て、バイオマス原料を使った新しい種類のナノセルロース対応バイオナノ肥料を実証を行うとの記事が掲載されました。
1 月 3 日に科学技術情報サイト Innovateli に掲載された記事によりますと、世界中の膨大な量のバイオマス廃棄物を再利用しながら、作物収量を改善するための、低コストで持続可能な肥料を開発・実用化するとともに、温室効果ガスの排出を増やし、地下水を汚染する化学肥料の排除しようとしているそうです。クイーンズランド大学は、ポリマー・ナノ複合材料の研究をリードしていることから、その原料としてバイオマス廃棄物を使う計画のようです。
ただ記事の内容からは、ナノセルロースがどのように使われるのかは、読み取れませんでした。
詳細は元の記事をご覧ください。