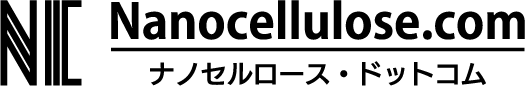ナノセルロース、セルロースナノファイバー(CNF)、セルロースナノクリスタル(CNC)、バクテリアナノセルロース(BNC)に関する、国内・海外の最新ニュースを掲載しています。こちらは 2020 年 6 月に報道されたニュースを、新しいものから順に掲載しています。
- 1 ナノセルロースをウエラブルセンサーの材料として使用(2020年6月30日)
- 2 セルロースナノクリスタルがアルコール消毒ジェルの増粘剤に採用(2020年6月29日)
- 3 パームヤシからのCNFでPEとの複合材料を試作(2020年6月28日)
- 4 ナノセルロースを使った木材のコーティング剤の開発と農業廃棄物の利用(2020年6月18日)
- 5 ナノセルロースをポリマーに添加する際の溶剤を減らす技術(2020年6月16日)
- 6 草野作工のバクテリアナノセルロースを和菓子に採用(2020年6月7日)
- 7 花王がセルロースナノファイバーを添加した高機能樹脂の供給を開始(2020年6月5日)
- 8 CNCを使った3Dバイオプリンティングでサンゴを模倣(2020年6月5日)
- 9 ミドリムシのナノファイバーを愛媛の紙加工会社が生産(2020年6月4日)
ナノセルロースをウエラブルセンサーの材料として使用(2020年6月30日)
スイス連邦材料試験研究所(EMPA)が年 4 回発行する Empa Quarterly (2020 年 6 月号)で、EMPAが進めているウエラブルセンサーによる人の健康管理に関する研究が紹介されています。
これは D-sense プロジェクトと呼ばれ、バイオミメティック・メンブレン分野の研究者とセルロース・木質材料分野の研究者が参加して進められているものです。研究の目的は、人の体に容易に装着できるウエラブルセンサーによって、アスリートの体調管理、睡眠時の体調管理を行うほか、薬を少しずつ放出するためのデバイス(着る薬)などの開発も行われています。
ここでセンサーとの材料として使われているのがナノセルロースです。ナノセルロースに銀ナノワイヤーを混ぜて 3D プリントすることで、負荷(伸び、縮み)や圧力を正確に測定することができます。ナノセルロースは生体適合性があるため、直接皮膚に接触する材料として適しているとのことです。
全文は EMPA のホームページからご覧いただけます。
セルロースナノクリスタルがアルコール消毒ジェルの増粘剤に採用(2020年6月29日)
新型コロナウイルス感染症により、アルコール消毒ジェルの需要が急拡大しており、ゲル化剤として添加されるカルボキシビニルポリマー(カルボマー)の確保が難しくなっています。カナダの CelluForce では、セルロースナノクリスタル(CNC)をカルボキシビニルポリマーの代替品として使用することを考え、同社の CNC であるCelluForce NCC® の性状を改良することで、アルコールゲル製造業者に採用されました。
パームヤシからのCNFでPEとの複合材料を試作(2020年6月28日)
金沢工業大学のニュースリリース(2020 年 4 月 21 日付)によると、同大学ではマレーシアプトラ大学(UPM)と MOU を締結し、パームヤシから作ったセルロースナノファイバー(CNF)をプラスチックに混ぜて、ナノコンポジットを製造する研究を進めているとのことです。このほど発表された国際共著論文では、パームヤシの CNF とポリエチレン(PE)のナノコンポジットを二軸スクリュー押出法で製造し、機械的特性などを調べています。
詳しくは同大学のニュースのページをご覧ください。
なお、UPM(University Putra Malaysia)は農学分野で優れた業績を上げている大学で、マレーシアの主要産業であるパームオイル生産で発生する残渣の有効利用に取り組んでいます。パームヤシから油分を抽出した残渣は主にエネルギー利用されていますが、さらに付加価値の高い物質を生産するという観点から、セルロースナノファイバーの製造研究に取り組んでいます。
ナノセルロースを使った木材のコーティング剤の開発と農業廃棄物の利用(2020年6月18日)
フラウンフォファー研究所木材研究所(WKI)のプレスリリース(5 月 19 日付)によると、WKI が参加する国際研究チームでは、農業廃棄物からナノセルロースを生産し、効率よく利用するプロセスについて研究を進めているとのことです。
この ValBio-3D プロジェクトの目的は、従来燃やされていた農業廃棄物を、高品質のアプリケーションに変え、それらをできるだけ効率的に使用することです。バガスとマツのおがくずからナノセルロースを製造し、それらをバイオプラスチックまたはコーティングに使用する方法を開発しました。
アルゼンチンの Instituto de Materiales de Misiones は、リグノセルロースの分解と基本的な化学物質の分離のためのプロセスを開発しました。
チリのラフロンテラ大学は、バイオプラスチックと基礎化学物質のバイオテクノロジーによる生産プロセスを開発しました。
フィンランドのVTTは、セルロースからナノセルロースを製造し、さまざまなバイオ複合材料で使用できるように最適化しました。
WKIはナノセルロースがバイオ複合材料とコーティング剤の製造にどのように使用できるかを研究しました。
そしてペルーのカトリック大学は、ライフサイクルアセスメントと経済性の評価を行いました。
研究の結果、ミクロフィブリル化セルロース(MFC)(=セルロースナノファイバー)で木材をコーティングすると、水蒸気透過性が向上し、コーティングの通気性が向上することがわかりました。後継プロジェクトでは、特別に変更されたナノセルロースを使用した木材の防火コーティングが開発されます。研究目的は、防火性能の耐久性を伸ばすことにあります。
詳しくは WKI のプレスリリースをご覧ください。
ナノセルロースをポリマーに添加する際の溶剤を減らす技術(2020年6月16日)
アメリカの Perdue 大学の Research Foundation News(6 月 15 日付)によると、同大学工学部の Jeffrey Youngblood 教授らは、ナノセルロースをポリマーに添加する際の溶剤の使用量を減らす技術を開発しました。
これまでナノセルロースをポリマー中に分散させるためには溶剤を使う必要があり、新たなプロセスや装置を追加する必要がありました。
開発された技術では、ポリマーの溶融処理中にナノセルロースを分散させる溶剤として、もともとポリマーに含まれる添加剤を使用します。すなわち可塑剤などのポリマー材料の添加物にナノセルロースを混合し、それをポリマーに配合します。
これにより、ポリマーにナノセルロースを添加する際に新たな溶剤を使用する必要がなく、親水性ナノセルロースと疎水性ポリマーの均質な混合物を得ることができます。この技術は、自動車産業で使用されるナイロンや食品包装で使用されるポリ乳酸とエチレンビニルアルコールコポリマーなど、さまざまなポリマーに適用できるとのことです。
詳しくは同大学のウェブサイトをご覧ください。
草野作工のバクテリアナノセルロースを和菓子に採用(2020年6月7日)
神奈川県小田原市曽我の老舗和菓子店 正栄堂 が、草野作工が製造・販売するバクテリアナノセルロース(BNC)、ファイブナノ® を添加した和菓子を開発し、5 月から販売していることが、神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙タウンニュース®(6 月 6 日版)で報道されました。
バクテリアナノセルロースの微細繊維が多くの水分を包み込むため、和菓子の保存期間を延長でき、製品をより遠方まで配送することができることに加え、製造ロスの減少にもつながるということです。また食感の向上という利点もあります。バクテリアナノセルロースが添加された 五郎力餅 などは、同社の本店と直営店で購入できます。
なお、ナノセルロースが添加されたことを公表した和菓子は、田子の月(静岡県富士市)のどら焼き、坂根屋(島根県出雲市)の和菓子に続いて、3 件目となります。
花王がセルロースナノファイバーを添加した高機能樹脂の供給を開始(2020年6月5日)
花王は表面改質し疎水性にしたセルロースナノファイバー(CNF)を樹脂に均一分散させて機能を高めた樹脂を、LUNAFLEX(ルナフレックス)という名称で販売を開始しました。
CNF は親水性のため、疎水性の樹脂に混ぜるためには、CNF の表面を疎水性にする必要があります。量子化学計算による構造予測に基づいた「デュアルクラフトシステム」と呼ばれる CNF 界面計算技術で、濡れ性と立体反発の観点で選定した 2 種類の修飾基を CNF の表面に結合させる方法により、少ない修飾基の量で疎水性を付与することができるようになりました。
CNCを使った3Dバイオプリンティングでサンゴを模倣(2020年6月5日)
セルロースナノクリスタル(CNC)を混ぜたポリエチレングリコールジアクリレートを使って、サンゴの微細構造を模倣した構造体を 3D バイオプリンティングで製造し、これを微細藻類の培養に用いたところ、光子の滞留時間が増加することで微細藻類の光吸収が促進されたため、最大細胞濃度が 10 倍、成長速度が 100 倍になったとのことです。
内容は Nature Communications に掲載された論文と、研究を実施したケンブリッジ大学のホームページに掲載されています。将来は微細藻類を使ったエネルギー生産への適用も考えられるとのことです。このようなナノセルロースを使った 3D バイオプリンティングの研究は世界中で行われています。
ミドリムシのナノファイバーを愛媛の紙加工会社が生産(2020年6月4日)
愛媛県四国中央市の紙加工業、スバルが、ミドリムシのナノファイバー生産に乗り出したとのことです。ミドリムシは微細藻類の一種でユーグレナとも呼ばれます。産経新聞電子版(6 月 3 日付)に掲載されました。
一時、バイオ燃料を生産する目的で研究が行われていましたが、現在では主に健康食品として流通しています。ミドリムシにはパラミロンという多糖類が含まれています。セルロースはグルコースが β1,4 結合でつながった水に溶けない多糖類ですが、パラミロンはグルコースが β1,3 結合でつながった多糖類で、やはり水には溶けません。またパラミロンはユーグレナ属にのみ存在するといわれています。
このパラミロンを含んだ健康食品が、すでに複数のメーカーから発売されていますが、スバルは宮崎大学が発見した株を使って、グルコースを原料にして培養し、パラミロンナノファイバーを大量生産するということです。